コメント
この記事へのトラックバックはありません。
岩槻郷土資料館一階の廊下に展示してある「唐箕(とうみ)」は、収穫された稲などを選別する際に、風を送ることによって、玄米ともみ殻や塵芥などをより分けるための農具です。
もともと、稲などの穀物を選別する作業には竹や籐などの皮で編まれた「箕(み)」が使われていました。
稲などの穀物を「箕」に入れ、上下させることによって、風でもみ殻や塵芥などの軽いものを飛ばし、選別が行われました。
この「箕」で行う作業を機械化したものが「唐箕」になります。
上部につけられた漏斗状の受け入れ口から、稲などの穀物を入れます。
円形の胴の中に把手と直結した羽根がついており、把手を回すことよって羽根が回り、風が起こることによって、選別が行われます。
実りがよく重さのあるものは、風に飛ばされずに、下に落ち、不要な実りの悪いものやもみ殻などの軽いものは風によって、別の部分から吹きだされていきます。
軽いものほど風に飛ばされやすく、重いものは飛ばされにくいという性質をうまく利用し穀物を選別し、より作業効率を考えた道具といえます。
展示している「唐箕」には、受け入れ口から中に入っていく穀物の量を調節することができ、さらに工夫がなされています。
江戸時代には使われたようで、時代を追って、このような様々な工夫がなされていきました。
しかし、「唐箕」を使った作業で、選別が十分に行われたわけではなく、さらに様々な「篩(ふるい)」によって選別が行う必要がありました。

この記事へのトラックバックはありません。
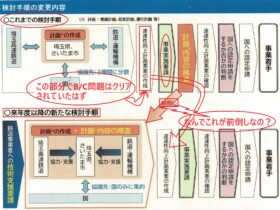
2024-4-12

2024-4-12

2024-4-12

2024/4/12
断念…地下鉄7号線の岩槻延伸、年度内は申請できず さいたま市議会
2024/4/12
正月襲った能登半島地震 食事が提供されない石川県
2024/4/12
おもしろ人物紹介 「失って分かる『当たり前』への感謝」
2024/4/12
「小さなお話」応募作品③ 「ミルクシンフォニー」 新井俊一
2024/4/12
新・「脳トレ」にチャレンジ!③
2024/4/12
断念…地下鉄7号線の岩槻延伸、年度内は申請できず さいたま市議会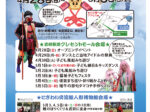
2024/4/12
端午の節句
2024/4/12
手作り展開催
2024/4/12
健康づくり教室(女性限定)Copyright © WEB ら・みやび 岩槻 All rights reserved.

この記事へのコメントはありません。