コメント
この記事へのトラックバックはありません。
江戸時代後期は、疱瘡の流行、火山の噴火(冨士山、浅間山など)、天候不順による凶作、米穀など諸物価の高騰は、小商いで生計をたてたり、人足などの賃稼ぎしている人々が生活に困窮し、穀物問屋や富裕な家々を打ち壊すという暴動が各地で発生しました。
岩槻宿では天保七年(一八三六年)八月二十一日の夜、生活に窮した人々が一斉に蜂起し、穀物問屋や富裕の家々を打ち壊す大騒動が発生しました。
この時の要求の一つに米の安売りなどがあり、岩槻宿町役人などは各町内ごとに対策を協議し、穀類を供出して施米や米の安売りなどを実施してこの騒動を鎮めました。
この穀類の供出について意見が対立し、さらに騒動が激化したのが新町です。
岩槻宿騒動発生後の八月二十三日新町では、町内の光明院に人々が集まり評議を行いました。
評議の席上で触頭平吉は、「当春以来打ち続く雨天にて諸作物は不出きで、田方は凶作のありさまで、米穀値段が格外の高値となり、水飲み百姓や日稼ぎの者どもが心得違いを致し、乱暴打ちこわしにおよんだ。
ついては物持ちどもは勿論町内一同は、余米または貯めている穀類を差出、眼前の困窮者に施し乱法を鎮める。
政吉、太郎左衛門は、相応の暮らしをしているので米十俵づつ差出し、困窮しているものも少々差し出す」という提案でした。
この評議の場に参加していた医師の良哲は、「物持ちどもと二軒の儀は最もであるが、困窮人の出穀いたす儀はいわれなきことで、政吉は二十一日の夜居宅を打ち壊され、太郎左衛門同様に十俵の出穀は相応ではなく、困窮人を相除き、取続く者より救米を差し出すべき」と主張した。
この良哲の意見に対し、平吉ら八人は、評議せず、声高らかに悪口をのべ、顔色を変え評議の場から立ち去り、評議の場は解散となりました。
この後、平吉ら退場者は、良哲の居宅に押し寄せ乱法に打ちこわし、眼前の家作、其の外薬箱・戸障子・建具・襖等を往来に投げ出し悉く踏崩し、良哲の店(たな)に居住していた家人の源七宅も打ち壊わし、夜八ツ時(午前二時)頃引き上げました。
この頃の良哲は、もともと困窮していたが穀の貯えなどもなく困窮の救けについての考え方を述べたものです。
良哲は、岩槻藩役人に訴え検分を受けましたが、大勢の人が良哲を打ち殺すとの風聞に、この日の夜中に家の者は市宿町の親類へ、良哲は真福寺村の親類へ身をひそめました。
この一件は、平吉ら打ちこわし人への科はなく、良哲の家人源七が手鎖り町内預けとなりました。
これを知った良哲は、不当な申し渡しだと岩槻藩役人に抗議しましたが退けられました。
これを不服とした良哲は、町役人の奥印も受けないまま、町役人、岩槻藩役所を経ずに直接奉行所に訴えたのです。
直接奉行所に訴えることは“越訴”または“かけこみ訴訟”と称し違法でした。
光明院は、新町の中ほどにあり、市宿町弥勒寺の末寺で稲荷山光明院といい、本尊に不動をお祀りしていましたが、明治初期廃仏毀釈により廃寺となった。
【文責・飯山実】
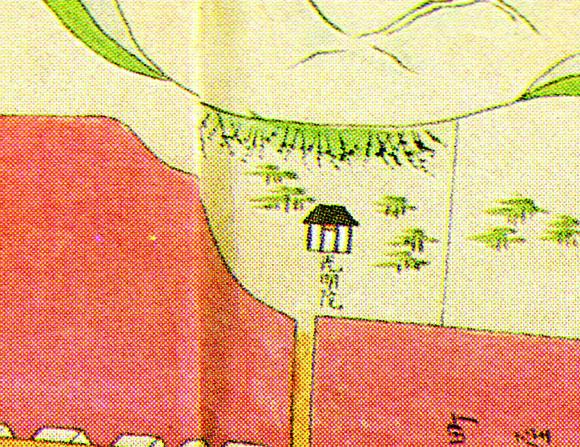
この記事へのトラックバックはありません。
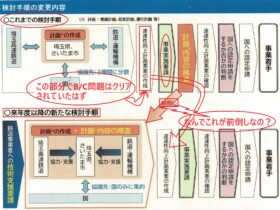
2024-4-12

2024-4-12

2024-4-12

2024/4/12
断念…地下鉄7号線の岩槻延伸、年度内は申請できず さいたま市議会
2024/4/12
正月襲った能登半島地震 食事が提供されない石川県
2024/4/12
おもしろ人物紹介 「失って分かる『当たり前』への感謝」
2024/4/12
「小さなお話」応募作品③ 「ミルクシンフォニー」 新井俊一
2024/4/12
新・「脳トレ」にチャレンジ!③
2024/4/12
断念…地下鉄7号線の岩槻延伸、年度内は申請できず さいたま市議会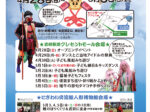
2024/4/12
端午の節句
2024/4/12
手作り展開催
2024/4/12
健康づくり教室(女性限定)Copyright © WEB ら・みやび 岩槻 All rights reserved.

この記事へのコメントはありません。